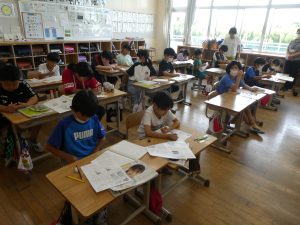お昼ご飯は一緒に活動した4年生、5年生と食べました。




食事中もジェスチャーを使って食べ方を教えたり、片付けの仕方を教えたりする姿が見られました。
午後は3年生と体を動かしながら、協力して活動しました。




「もっと遊びたかった!」「また来てくれるかな~」と交流を楽しんでいる様子でした。


バスが見えなくなるまで大きく手を振ってお別れしました。
今回の交流や経験が、他国の習慣や文化への関心につながったり、進んでコミュニケーションを図ろうとする態度を養うことにつながったりしました。この学びを、これからの生活にも生かしていければと思います。